わたしは、君が代という歌を好まなかった。
しかし、今は少し認識が変わった。
君が代の元歌は下記であるという話がある。
我が君は
千代に八千代に
さゞれ石の巌となりて
苔のむすまで
-古今和歌集 読み人知らず-
歌人は藤原朝臣石位左衛門というのは、とってつけた嘘だと思う。
そして、これは恋文であるという説がある。
さもありなんと思う。覚悟のこもった恋歌である。
しかし、わたしはわたしの訳をつけたい。
考察。
我が君・・これは気にかかる。改ざんではないか。
「君」は「恋」ではないのか。
さざれ石とは小さな石。細石。しかし、この時代に、字余りの短歌を詠むとは思えない。これは多分「ざれ石」であろう。
千代に八千代に、これも伝本では、千代にましませ、となっている。
巌は大きな岩、大きな岩の塊。これも恋の歌としては無粋であると思う。
「巌となりて」は「岩音鳴りて」であろう。
すると、この歌はこうなる。
「我が恋は
千代にましませ
ざれ石の
岩音鳴りて苔のむすまで」
この恋歌を
わたしなりに解釈する。
「わたしの恋は、永遠に続きます。
川の小さな石がかすかな音を立て続け、
そこに苔が生えるまで。」
これなら
森の奥の小川は静かに流れ続け、時折小石が音を立て、時が流れていく。
そういう風景が浮かび上がってくる。
森の奥であれば、片思いであるということも想起される。
清い歌だと思う。
これが恋歌でなかった場合。
古代語では、「き」は男性「み」は女性を示す。
君とは、相手を親しみ敬う言葉でもある。
「我が君は
千代に八千代にざれ石の
巌となりて苔のむすまで」
「わたしたち同胞(はらから)は、男性も女性も、
何代生まれ変わろうとも、
小さな石が大きな岩となるがごとくに、結束し、助け合おう。
その大きな岩に苔がむすまで、永遠に。」
こうなるのではないか。
これなら立派な国歌になる。
まぁ、結論を出す気はないが、センチメンタルなわたしは恋歌説に流れがちだ。
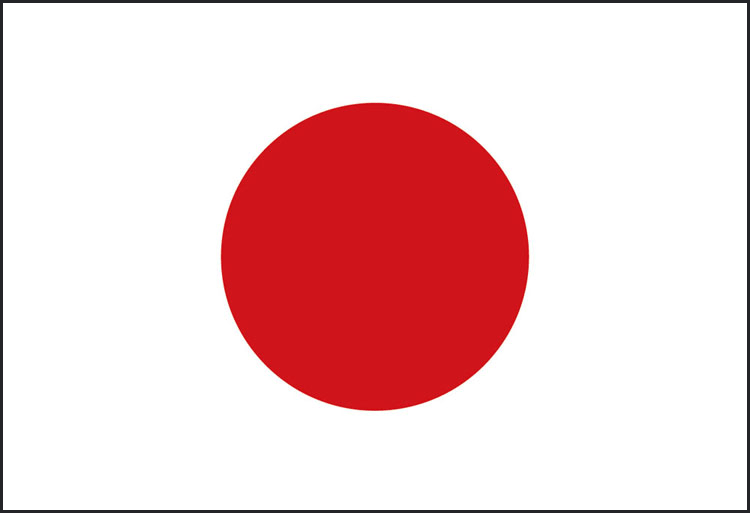
これはわたしが聞いた中で最も打ち震えた演奏である。
