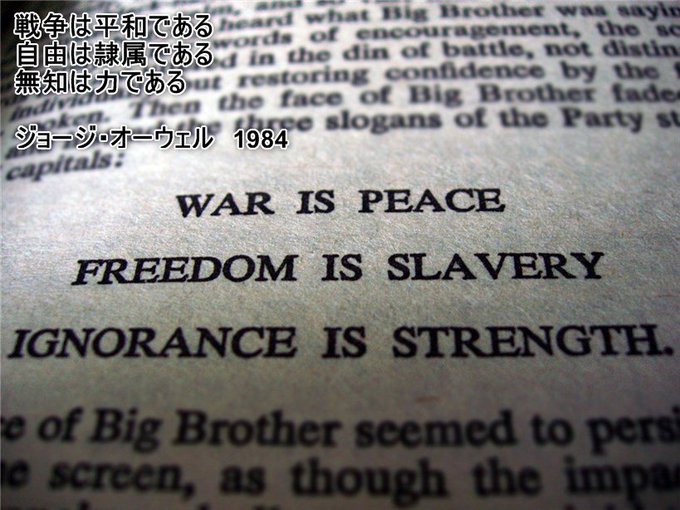さて、DPP4阻害薬を飲んでいたわたしに次に起きたことは眼底出血である。両目ともに広範囲に眼底出血が見られ、何度もレーザー治療に通った。その頃である。わたしはDPP4阻害薬を止めた。一応、両目の治療が済み、1ヶ月ほど経った頃、わたしは検査のために眼科を訪れた。新たな眼底出血は起きていなかった。眼科の医師は「血糖値のコントロールがうまくいっているのだろう」と言ったが、血糖値は以前より上がっていた。DPP4阻害薬を止めたことが、これほど顕著に眼底に好影響を与えることにわたしは驚いた。過剰なインスリンは細胞を傷つける。これはわたしにとっての真実だ。

Bottom / 他人の幸せを見ることは己の幸せである
To see the happiness of others is my happiness 南海之獏